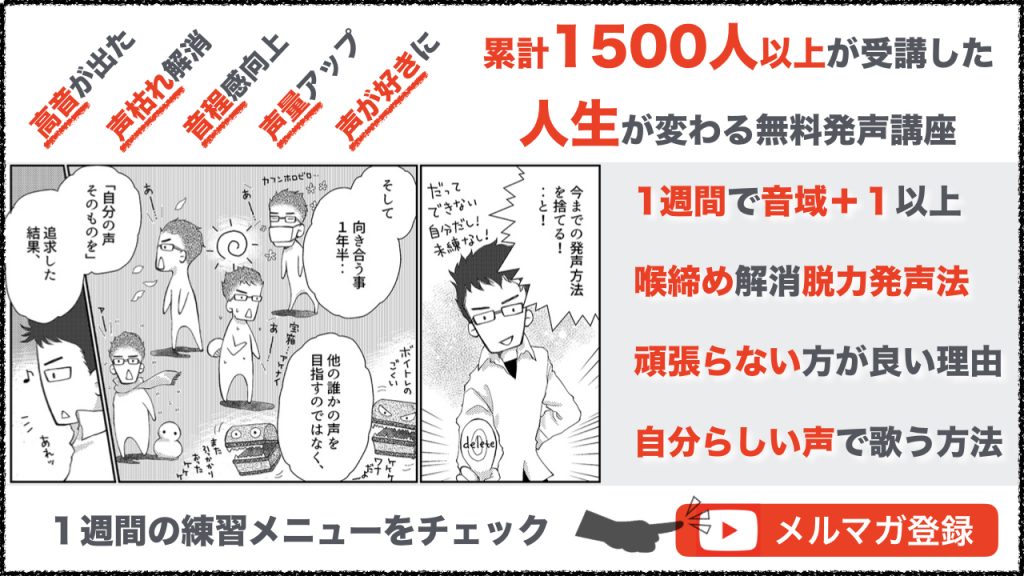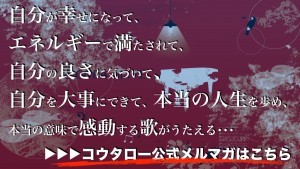- 信頼される声とは?
- 低い声
- 大きな声
- 高低差
- リズムとスピード
- 滑舌
- 指揮者の視点
- リーダーボイスレッスン

経営者やリーダーにとって、人の心を動かすための「伝える力」は必要不可欠なものです。
情報発信、顧客への商品紹介、部下へのレクチャー、ビジョンを伝えるとき……
そのすべては、「声」と「言葉」という武器を使い、迫力、説得力、威厳を以て「話す」ことに他なりません。
でも、社長だからと言って当然のように風格があり、説得力のある話し方ができるのかと言うと、そうではありませんよね。
「声がうまく出ないせいで威厳を保てない」、「リーダーなのに人前で話すことが苦手」、「どんな声が人の心を動かすのか」
今回は、そんな悩みについて、一緒に解決していきましょう。
経営者の風格が感じられない話し方!?マイナスに捉えられる特徴!
話の内容がどれほど立派であっても、声に風格が備わっていなければ伝える力は半減してしまいます。
立場上コミュニケーションを取らざるを得ないのに、話し方や声の質次第で部下や顧客に与える印象が変わってしまうというのは、悩みの種ですよね。
小さく弱々しい声で「ふざけるな!」と言われても怖くありませんし、自信なさげに早口で「この商品はすごいんです」と言われても、本当かな?と疑ってしまいます。
マイナスの印象を与えてしまう話し方の特徴にはどんなものがあるのか、下記をご覧ください。
・高いトーンの声は、言葉に重みがなく耳障り
・語尾を伸ばすと品位が感じられない
・小さな声からは自信を感じられない
・間延びしたテンポの悪い話は耳に入らない
・早口すぎると慌てているように感じる
・口数が多すぎると軽く感じる
・ボソボソした話し方は内容が理解できない
・抑揚がないと感情が伝わらず退屈
・落ち着きのない声は冷静さを感じられない
・「あー」「えー」が多いと聞く側にストレスが溜まる
・「慣れないもので…」など前置き保険は信頼性を下げる
このように、話し方によっては、軽視されたり、信頼性を失ってしまったり、そもそもの話の内容を理解してもらえない、話を聞いてくれない、などの弊害が発生してしまうんです。
指導する立場、情報を発信する立場など、大勢の聞き手を対象として話さなくてはならない場合、その機会を最大限に利用して、プラスの役割を果たしたいものですよね。
耳を傾けたくなる「声」や「話し方」ってどういうもの?
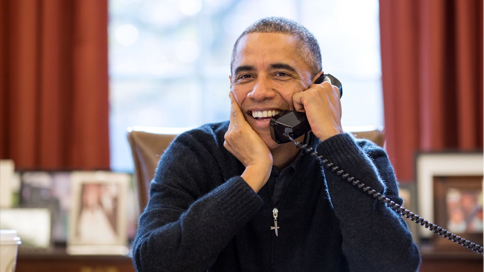
相手にとって聞き取りやすく、内容が伝わりやすい話し方をするためには、「話の内容」はもちろんのこと、「話すスピード」、「滑舌」、「声の大きさ」、「間」、「リズム」などをコントロールしなければなりません。
スピーチ力について特に有名な「Yes, We Can」でお馴染みのオバマ大統領を例にとってみましょう。
彼は「ほどよく低く、通りのよい、説得力のある響く声」と言われています。
日本のアナウンサーも、言葉に落ち着きと説得力を持たせるために、元々の声よりも低いトーンで話すというテクニックを使っていますね。
まず何よりも、聞き手にはっきりと伝わる、少し低めの落ち着いた声で話すということが重要なんです。
次に、「緩急のリズム感がある話し方」です。
オバマ大統領の話し方には、歌のような耳に心地よいリズムがあるのだそうです。
日常会話の中で、発した言葉がたまたま5・7・5になったときや、意図せず韻を踏んだとき、深く印象に残ってしまうことがありませんか?
相手の心を動かすためには、リズムも大切なんですね。
また、オバマ大統領のスピーチでは「子供から年配の方まで理解できる簡単な単語」が使われています。
言葉の選択が重要ということでもありますが、まわりくどい話し方や、難しい言い方をしない、というシンプルなテクニックとも言えます。
「声そのもの」の魅力を最大限に引き出そう!

スピーチについていろいろなテクニックはあれど、何より大切なのは、あなた自身の持つ最大の武器、「声」です。
声のせいで想いが伝わらないなんて、もったいないですよね。
魅力ある伸びやかな声を引き出すことができれば、きちんと聞き手の耳に届き、話すことが楽しくなり、多くの人に伝えたい言葉を余すことなく発信できるようになるのではないでしょうか。
声帯や咽喉などの発声器官に異常がないのに、病気が原因で上手く声が出ない、もともと声が小さくてどうしようもない、と諦めている方。
あなたの中にも、ちゃんと魅力ある声が眠っているんです。
そこで「病院で声を治してもらう」という選択をしてしまうのは、ある意味間違いであると言えます。
本当に困っていて、医者なら間違いはないだろうと思って通院しても、原因不明のまま経過観察になってしまったり、見当違いの投薬や、外科的な処置をされたりする恐れがあるからです。
病院で的外れな治療をされる前に、あなたの声の不安を取り除き、魅力を引き出すトレーニングを行ってみませんか?
これからリーダーのためのボイストレーニングについて、一緒に学んで参りましょう!

主導的立場にある人は、相手が部下であれリスナーであれ、大勢の人たちの心を動かし、導かなくてはなりません。
リーダーたるもの、正しくて、頼りがいがあって、責任感があって、信頼するにふさわしい人間でなければいけませんよね。
大勢の人の前で話すとき、聞き手は目と耳を使って無意識のうちにあなたを審査し、評価しています。
評価されるなんてイヤだな~と思うかもしれませんが、「声」で印象を変えられるのならば、それを逆手に取ってしまえば大きなチャンスなんですよ!
声の魅力を引き出し、リーダーボイスを手に入れる6ステップを、一緒に踏み出してみませんか?
その1「低い声を出そう!」←今回はコレです!
その2「大きな声を出そう!」
その3「高低差をつけよう!」
その4「リズムとスピードを調節しよう!」
その5「滑舌をよくしよう!」
その6「指揮者の視点で全体を調整しよう!」
修羅場をくぐったり、場数を踏んだり、身体を鍛えたりしなくても「この人についていきたい!もっと話を聞きたい!」と思わせるほどの説得力と信頼感が、声によって得られるとしたら、喜ばしいことですよね。
今日の1歩は、リーダーボイス習得へのステップ1、「説得力と信頼感を生む、低い声を出そう!」です。
高い声には威厳を感じない!?

高いトーンの声は、説得力がないと言われています。
また、女性や子供に近い印象があるため、「頼りがい」というイメージからは遠ざかってしまいますよね。
甲高い声というのは、本能的に危険や恐怖が迫っていたり、興奮していたりするときに出るものなので、瞬間的には周囲から注目されるのですが、ずっと高いトーンで話し続けると、聞き手は常に安心感のない状態になってしまいます。
また、差し向かいで話したとき、相手の声のトーンが高い場合、人は無意識のうちに「自分は上の立場だ」と思いやすいんです。
例えば、客として訪れた車屋や、旅館の受付など、おもてなしを「する方」と「される方」では、前者の方がにこやかで高い声、低姿勢になりがちですよね。
高い声に比べて、低い声の人ほど「頼りがいがある」「みんなを導いてくれる」「パワーがある」「落ち着いている」という印象があり、結果的にリーダーとして好まれるという研究結果があります。
声が低いと、話の内容に説得力や重みが生まれるんです。
イギリス初の女性首相であり、「鉄の女」とも呼ばれたサッチャー元首相も、スピーチに説得力を持たせるため、低い声の出し方を学んでいたそうです。
子供が悪いことをしたら、親御さんはいつもより低い声で、言い聞かせるように叱りますよね。
これも、威厳や風格を漂わせ、従うべき目上の人間であることを教えるためのテクニックなんです。
人々はなぜ低い声にリーダーとしての魅力を感じるのか?それは、本能に訴えかけるシンプルな印象と言えます。
女性が「男らしい男性」に惹かれるのは自然の摂理ですが、話し方が低音な人ほど、男性ホルモンの分泌が多く、男らしくたくましい人間なんだと思い込んでしまう可能性が大きい、ということですね。
また、動物の世界でも、強さや体格が抜きん出ているオスこそが群れのリーダーになりますよね。
男性から見た場合も、声の低さは風格の判断材料になるわけです。女性にも男らしさを感じるの?となると、おかしな話に思えますよね。
「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざがありますが、実は人間って、常にそれに近い「理論の飛び石」とも言える思考を行っているんです。
例として、安く売っている宝石屋さんの話をしましょう。
あるところに、宝石屋さんがありました。扱っている宝石はすべて本物で、よいものです。店主はみんなに喜んでほしくて、安い値段をつけました。
なのに宝石はちっとも売れず、店はずーっと赤字続き。結局、お店は閉めることになりました。
店主は2分の1の値段で叩き売りするよう部下に伝え、出掛けました。しばらくして、店に帰ってくると、宝石はひとつ残らず売り切れ。ここまで安くすれば売れるんだなあ、と店主は思いました。が、レジを見ると溢れんばかりのお金が!なんと部下が指示を聞き間違えて、2倍の値段で売っていたのです。
というお話です。人間はいつもたくさんの情報に囲まれて、それを休む暇もなく論理的に処理しなければなりません。
すべてのことをいちいち1から10まで考えると疲れてしまうので、「値段が高い=品質が高い」といった思考のショートカットをしてしまうんです。
おかげで、意外と簡単に印象操作されてしまうんですね。
「低い声=信頼できる」というのも似たようなもので、よくよく考えれば、必ずしもイコールとは限らないんじゃない?というようなことまで、関連付けてしまうのです。
男女ともに声が低いほどリーダーにふさわしいという印象を持たれるからくりは、そういうわけでした。
それでは、リーダーボイス習得への第一歩、風格、説得力、信頼感を増すために「低い声を出そう!」を、動画で解説させて頂きますので、ご覧下さい。

その1「低い声を出そう!」
その2「大きな声を出そう!」←今回はコレです!
その3「高低差をつけよう!」
その4「リズムとスピードを調節しよう!」
その5「滑舌をよくしよう!」
その6「指揮者の視点で全体を調整しよう!」
多くの人に情報を伝える立場にある方にとって、声の魅力を引き出すことは何よりの武器になります。
リーダーボイスを手に入れるための6ステップ、前回は説得力や風格が感じられる低い声の出し方についてでした。今回は、その2「大きな声を出そう!」です。
単純明快!大きな声が出ない原因は、大きな声を出さなかったから!?
大声を出す機会って、意外と少ないですよね。
大きな声を出すのが苦手な方は、年を重ねるにつれて苦手意識が強まっていくばかりだと思います。
「お腹から声が出ていない」なんて言葉は良く聞くけれど、今までずっと同じ話し方でやってきたのに、今さら変えるなんて億劫だし、一朝一夕には出来そうにない……と諦めてしまう方も多いんじゃないでしょうか。
もともと声が小さくて悩んでいる方は、
・オーダーを1度で聞き取ってもらえない、
・呼んでも店員さんが来ない、
・仲間同士で話すと自分だけ聞き返される、
・騒がしい場所では会話できない、
・返事を何度もやり直しさせられた、
など、いくつもの苦い思い出があると思いますが、そうした経験を重ねていくうちに、いつの間にか「伝わらない」ということに慣れてしまっていませんか?
慣れないことをするのはいつだって恥ずかしいものですし、かなりの勇気が要りますよね。
でも、多くの聞き手に情報を発信したり、大勢の部下を束ねたりする立場の人にとって、その要素はマイナスにしかなりません。
大きな声を出すだけで、自分に自信を持つことができて、人からも信頼されるとしたらどうでしょうか。
緊張しやすく、自分に自信がない人は、うつむきがちで声が小さいことが多いです。
しかし、それを逆手にとって、前を向いて声を大きくすることができれば、緊張が解け、声に自信を乗せて、人に届けることができるようになるんです。
「大きな声」には伝わる力が秘められている!

子供の頃、発表や合唱で先生から「もっと大きな声で!」と言われた経験はありませんか?
どうして大きな声を出す必要があったのか、基本に立ち戻って考えてみましょう。
社内でのプレゼン然り、会議での挨拶然り、多くの聞き手に対して何かを伝える場合、明瞭さは必要不可欠です。
声が小さければ、どんなに話の内容が良くても伝わりませんし、感情も伝わりませんよね。
「聞こえない声」は結局のところ「話していない」のと同じようなものなんです。
話を聞いてもらえない先生が、怒って教卓をバンバン叩く場面、見たことありませんか?
あれは、大きな音を出せば生徒が注目するという、反射的な反応を利用した、注意をひきつけるためのテクニックですよね。
同じように、大きな声で話すことは、まず聞き手の注意を引くという点においても、とても大切なことなんです。
初めに「みなさん、こんにちは!」と、大きな声で挨拶すれば、意識的に話を聞こうとしていなくてもつい耳が声を拾ってしまいますから、勝手に聞く準備が整ってしまうんですね。
また、ボリュームを上げることで、声そのものの熱意や迫力、威厳が増し、注目されますし、「元気」「活動的」「明るい」「たくましい」など、生命力がみなぎっているイメージを持たれます。
ただし、あまりに大きすぎて、うるさいな~と思われてしまっては逆効果ですから、「大きめ」程度が望ましいですね。
いざ!「大きな声」を出してみよう!

舞台で寸劇をやっているようなアミューズメントパークでは、稀に、観客席の中から舞台に上がるよう指名されるお客さんがいます。
一言、二言ではありますが、大観衆の前で台詞を言わなくてはならない、素人にとってはドキドキのイベントですよね。
指名されたお客さんが、舞台裏のわずかな時間で役者さんからアドバイスされるのは、「叫ぶくらいの気持ちで、大きな声で台詞を言って下さい」ということなんだそうです。
舞台役者さんたちは、観客席までよく届く大きな声を出していますが、聞いている側からすると、自分でも出せるような、ごく普通に話しているような声だと錯覚するくらいに自然で大きい声なんですね。
なので、舞台に上がったお客さんがそのつもりで普通に声を出しても、観客席にはちっとも声が届かないんだとか。
今後、話の内容に応じてボリュームを調節するような、細かな技法を使う機会がやってくると思います。
しかし、まずは何より土台として「大きな声を出せるようにする」という基本を身につけなければなりません。
「思い返せば大声を出す機会なんてなかった」「無理に出すと怒鳴ったような声になってしまう」など、大きな声についてなじみがない方も、「人にきちんと伝わる声の出し方」を動画で解説させて頂きますので、ご覧下さい!

その1「低い声を出そう!」
その2「大きな声を出そう!」
その3「高低差をつけよう!」←今回はコレです!
その4「リズムとスピードを調節しよう!」
その5「滑舌をよくしよう!」
その6「指揮者の視点で全体を調整しよう!」
リーダーボイスを手に入れるための6ステップ、前回までの分で低い声の出し方、大きな声の出し方を身につけることができたと思います。
今回は、その3「高低差をつけよう!」です。単調で平坦な声は心に届きません。
より豊かに感情を伝えるためには、自分自身の持つ声の幅、声域をきちんと把握して、コントロールすることが重要なんです!
人は言葉の意味だけでなく、声から感情を読み取っている!
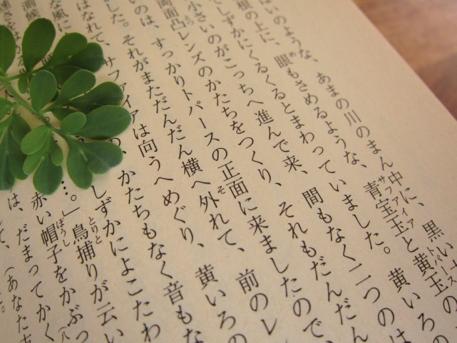
人間は、言葉の意味だけでなく、声の調子から様々な感情を読み取ろうとします。
同じ言葉であっても、声のトーンや大きさによって、聞き手に与える印象は変化するんです。
例えば「明日は食事会なんですよぉ……」と低い間延びした声で言われれば、面倒臭そう、または嫌がっているように感じますし、「明日は食事会なんですよ!!」と元気に言われたら、明るさや期待を感じますよね。
「棒読み」を代表とする単調な口調は相手を退屈させ、伝わる力を半減させてしまいます。
校長先生の話が退屈で、話の内容がまったく頭に入ってこなかった……なんて経験、ありませんか?
逆の立場になってみれば、大勢の前で話をする機会があるのに、そこで気持ちが伝わらないなんて、もったいない以外の何物でもないと思いますよね。
高い、低い、強い、弱い、大きい、小さい、をコントロールして、「抑揚をつける」、「メリハリのある声にする」ことが今回の目標です。決意、期待、怒り、熱意、希望など、大勢の人に対して感情を乗せた言葉を伝えるためには、豊かな声の表現力が必要なんです。
子供に読み聞かせる絵本や紙芝居って、大げさなくらいに感情を込めますよね。
プレゼンでも会議でも、ただ言葉を伝えるだけでなく、物語を演じるくらいの勢いがあれば、伝えたい想いが声に乗ると思いませんか?
高い声、低い声、小さい声、大きい声、どう使い分ければいいの?

人間の脳は常に複雑な処理を行っているので、実はあまり集中力がありません。
1日の3分の1以上、働いたり、勉強したりするのが当たり前になっていますが、全力で集中できるのはたったの15分程度と言われています。
小学生が退屈でそわそわし始めるのも15分経った頃です。
大人なら集中できるのかと言うとそうでもなく、子供のように露骨な態度を取らないだけで、サラリーマンだろうが、国会議員だろうが、退屈なものは退屈なんです。
気持ちを伝えたいのなら、まずは自分の話に集中してもらわなければなりません。
一方的に情報をぶつけるのではなく、相手に理解してもらいたいという気持ちで、それこそ子供に読み聞かせるのと同じように、「心をこめて分かりやすく」話すことが大切なんです。
感情を込めるのはもちろんですが、感情がきちんと伝わるようにするには、声を使い分けるテクニックが重要になってきます。
スピードや間、リズムについては次回のステップで説明させて頂くとして、声の「大きさ」「高さ」「イントネーション」に着目すると、下記のような印象や感情を聞き手に与えることがあります。
大きい声:教えたい、伝えたい、熱意、怒り、憤り、驚嘆、共感、パワフル
小さな声:言いにくい、伝えたくない、残念な、悲しい、呆れた、やるせない
高い声:お願い、話題の切り替え、機嫌が良い、明るい、元気、優しい
低い声:納得してほしい、威厳、真面目、真剣、信念、自信、不機嫌な、力強い、安定感
イントネーションは、話し手の自信のバロメータになります。例えば「黄色くて首の長い動物は?」と聞かれた場合に、答えに自信があれば「キリン!!」と言いますが、自信がなければ「キリン……?(かな?)」となりますよね。
人は自信がないことについて話すとき、やや語尾上がりになる傾向があります。
「○○!!」と語尾下がりに断言することは、自信の表れとして捉えられ、信頼感が増すんです。
どうすれば声に幅を持たせることができるの?

声に感情を込めるためには、「差をつける」「幅を持たせる」ということが重要になりますが、いまいち把握できないという方は、最初に下記の例で、自分になりに声を出して頂くと分かりやすいかもしれません。
・「大丈夫」という言葉をシチュエーション別に使ってみよう!
- 声を殺して泣いている友達を見つけたときの「大丈夫?」
- 痛いけど相手に弱みを見せたくないのでやせ我慢して「大丈夫」
- 悲鳴が聞こえて慌てて駆けつけたときの第一声「大丈夫!?」
- 同じミスを何度も繰り返す後輩に自分の仕事を任せて帰るときの「大丈夫?」
このように、同じ言葉でも、言い方によっては印象が変わりますよね?
意識して「高い声」と「低い声」を上手に使い分けることができないという方、いらっしゃると思います。
自分がいつも出しているトーンを基準にして、ハッキリと聞き取りやすく、もっと高い声、もっと低い声を出し、メリハリをつけて感情を乗せるためには、どうしたらいいのか?
動画で詳しく解説させて頂きますので、ご覧下さい!

その1「低い声を出そう!」
その2「大きな声を出そう!」
その3「高低差をつけよう!」
その4「リズムとスピードを調節しよう!」←今回はコレです!
その5「滑舌をよくしよう!」
その6「指揮者の視点で全体を調整しよう!」
リーダーボイスを手に入れるための6ステップ、その1~3まで、指導者らしい風格ある声の出し方、感情をより豊かに伝えるためのテクニックについてご紹介してきました。
引き続き今回は、速さ、リズム、間のコントロール方法について解説していこうと思います。
「速い」と「遅い」それぞれが与える印象って?
声の低さや大きさが同じでも、話すスピードによって聞き手に与える印象は大きく違います。
速いテンポは「ネズミ」、遅いテンポは「ゾウ」に例えると分かりやすいかもしれませんね。
ネズミはちょこまかとせわしなく、落ち着きがありませんが、俊敏で、周囲の変化を素早く察知します。
ゾウは、雄大で落ち着いていて、力強さもありますが、マイペースでのんびりしていますよね。
【話すスピードが速い人の印象】
≪プラスのイメージ≫
・頭の回転が速い
・元気で明るい≪マイナスのイメージ≫
・焦っている、緊張している
・興奮していて落ち着きがない
・話の内容に自信がない
・無駄口が多い
・自己主張が激しい
・神経質
【話すスピードが遅い人の印象】
≪プラスのイメージ≫
・落ち着きがある
・自分の意見を持っている
・力強く堂々としている
・分かりやすい
・冷静で用心深い≪マイナスのイメージ≫
・自分本位
・気が回らない
このように、どちらかと言うと早口の方がマイナスな印象を持たれがちですが、1対1の交渉など、相手に考える暇を与えずに相槌を打たせるという点においては、早口で説得力が高まるということもあります。
海外では、スラスラと早口で流暢に話す方が知的で好まれる場合もあるようです。
あまりにもゆっくりすぎると、のんびり屋さんと思われてしまうこともありますね。
とは言え、大抵の人は大勢の前で話すとき、有益な情報を伝えたいという気持ちや、勢い、緊張などによって話すスピードが考えるスピードに近づいてしまい、どうしても早口になってしまうものです。
マシンガントークという言葉がありますが、過度の早口は聞き取りにくく、相手が疲れてしまったり、せっかくの内容がきちんと伝わらなかったりする可能性があります。
社長や指導者などのリーダー的立場においては、「自分の意見をきちんと持っていて、冷静で、パワーがあり、周りに惑わされない」というイメージの方がふさわしいですから、基本的には遅いスピードの話し方が有利に働きます。
また、緊張しているとき、意図的に話すスピードを遅くすることによって、緊張がやわらぐという効果もあります。
しかし、極端に速ければいい、遅ければいいというものではなく、本当に大切なのは、ちょうどいいテンポと、内容によってスピードを調整することなんです。
「間」って何なの?どうやってリズムをつけるの?

リズミカルでテンポのよい話し方は、耳に心地よいものです。
脳には、ミラー・ニューロンという、共感や模倣を司る神経細胞があります。
テレビのハプニング映像で、盛大に転ぶシーンを見て「うわーこれは痛い!!」と思ったり、悲しいニュースを見て涙を流すことがあるように、私たちは、見たものや聞いたものに対して共感や同調をします。
ですから、緊張している人が浅い呼吸で機関銃のように勢いよく話していれば、聞き手にとっても休む暇のない、緊張感のある時間になってしまうわけですね。
早口で話されると、聞き手は話の内容を理解しにくくなります。
なぜかと言うと、情報量が多すぎて、吟味する時間を与えてもらえないからです。
早口になる原因としてありがちなのは、緊張して呼吸が浅くなり、少ない一息で一気に話そうとしてしまうケースです。
よく、「緊張したら深呼吸をしなさい」と言いますが、話すスピードには、呼吸も深く関わっているんですね。
また、ゆっくり話していても、「間」がないと早口な印象を与えてしまいます。
間は、聞き手が言葉を反芻して理解するための休憩時間のようなものです。
また、文章を区切り、読みやすくするために句読点が存在しているように、話の中に間を設けることで、分かりやすさが増します。
文章に段落があるように、まとまりを示すためにも間は必要ですね。
間を利用して、言葉を強調したり、聞き手を引きつけたりすることもできます。
例えば、クイズ番組によくある、正解発表の方法。「正解はAです!」と言うより、「正解は…………Aです!!」と、間を置いて発表しますよね。
これは、焦らすことによって期待感を高め、相手の心をぐっと引きつけるためのテクニックなんですね。
内容や反応によって、話すスピードや声の大きさ、高さを調整し、要所に間を置くことで、言葉はリズミカルになり、すんなりと聞き手の耳に入っていきます。
というわけで今回は、前回までのステップで引き出した本来の声を、間を置いたり、スピードを調整したりすることによって、より細かく自由に使う方法について解説させて頂きたいと思います。

その1「低い声を出そう!」
その2「大きな声を出そう!」
その3「高低差をつけよう!」
その4「リズムとスピードを調節しよう!」
その5「滑舌をよくしよう!」←今回はコレです!
その6「指揮者の視点で全体を調整しよう!」
前回までのステップで、低い声、大きな声、高低差、スピードについて解説させて頂きましたが、実はまだ、大事な基本が残っているんです。
リーダーボイスを手に入れるための6ステップその5、今回は、滑舌について学んでいきましょう!
声量は十分にあるのに、伝わらないのは何故!?
声は大きいはずなのに聞き返されることが多い、または、滑舌が悪いという自覚がある方。滑舌が悪くて何を言っているのかよく聞き取れないことほどもったいないことはありません。
何故なら、大勢を前にした演説や、動画や音声などの情報発信においては、1対1の対話と違って聞き返してもらうことができないからです。
一方的な発信となることが多いわけですから、必ず正確に伝えなければなりませんよね。
滑舌が悪い原因とは何か、どう改善すべきなのか。滑舌のよい発音をするためには、どんなトレーニングを行えばいいのか。まず、滑舌が悪い原因について詳しく見ていきましょう。

・口呼吸
口呼吸が習慣になっていると、口を閉じる筋力が弱まり、それが原因で発音に問題が生じることがあります。ボーッとしているときや寝ているとき、習慣的に口が半開きになっている人は要注意です。腹話術師が口を閉じたまま明瞭な発音をするように、実のところ、発音に関しては口が開いていれば良いというわけではないんですね。
・低位舌
口を閉じたとき、舌先が前歯の裏にあり、上顎に舌全体がつくのが「正しい舌の位置」です。舌の筋肉が弱まっていると低位舌になり、いわゆる「子供のように舌足らずな話し方」になります。さ行、た行、な行、ら行など、舌を持ち上げる音が正しく発音できないため、極端に表現すると、「そんなことありませんよ」が「しょんあこおあいましぇんよ」といった風になります。
・歯並び、噛み合わせが悪い
歯並びや噛み合わせが悪いと、発音の際に舌の位置が思うようにおさまらなかったり、隙間から空気が漏れてしまったりと、滑舌や発音の障壁となる場合があります。声を出す、喋る、という行為について考えるとき、舌と喉に意識が行きがちですが、「歯」も大切な部位なんですね。「上下前歯合わせて4本が抜けてしまったら、どんな風になるだろうか?」と、想像して頂ければ、歯の重要性が分かりやすいかもしれません。
・肺活量や呼吸法
日常的に浅い呼吸が習慣になっている場合、声が弱々しくなって全体的に不明瞭になることがあります。また、肺活量が少ないと声のパワーが口や舌に伝わらず、キレがなかったり、ぶれたり、絞り出したような、絡みつくような声になってしまいます。
・誤った発音方法
特に身体的な問題がないにも関わらず滑舌が悪い人は、元々、言葉を覚える際に発音の仕方を間違ったまま習得してしまった可能性があります。特に顕著なのが「い段の間違い」で、「き」「し」「ち」「に」「り」などを誤った舌の使い方で発音している人が多いです。スピードワゴンの小沢さんや、釈由美子さんなどもこれに当たると思われます。
滑舌を良くして、聞き取りやすく伝わりやすい声を手に入れよう!

客先でのプレゼンや会議でのスピーチ、部下への指示、音声や動画での情報発信、これらはどれも、伝えたい内容を余すことなく聞き手の耳に入れなければならないものです。
ニュースアナウンサーは聞き取りやすい話し方をしますが、それはシンプルに内容のみを伝えるものであって、個人的な感情を込めることはありませんよね。リーダー的立場となると、相手にとってただ聞き取りやすければいいというわけではありません。
聞き手は、単調な話を長々と聞かされたり、うまく聞き取れない状態が続いたりすると、退屈になって集中力と興味を失います。
そうさせないためには、「もっとこの人の話を聞きたい!」と思ってもらえるように、滑舌の良い、ハキハキとキレのある声を出し、そこに感情を乗せなくてはならないんです。
前回までのステップで学んできた声の使い方と合わせることによって、強く揺らぎのない確固たる信念を持ち、自信に充ち溢れ、重厚で芯があり、信頼性のある、テンポの良い、つまりは「リーダーらしい」話し方が完成します。
次回、最終ステップとして全体的な細かいテクニックについて解説させて頂きますが、リーダーボイス習得の基本については、今回で一通りおしまいです。
それでは、滑舌の良い話し方をするためにはどうしたらいいのか、動画で解説させて頂きますのでご覧下さい!

その1「低い声を出そう!」
その2「大きな声を出そう!」
その3「高低差をつけよう!」
その4「リズムとスピードを調節しよう!」
その5「滑舌をよくしよう!」
その6「指揮者の視点で全体を調整しよう!」←今回はコレです!
リーダーボイスを手に入れるための6ステップ、今回は総括として、指揮者の視点に立って行う、全体的な調整についてのお話です。
「指揮を取る」という言葉が指し示すように、集団の上に立ち、統率をとることこそがリーダーの重要な役割です。
これまでのステップでは、リーダーらしさを身につけたり、人を惹きつけたりするテクニックについてお話して来ましたが、今回は、自分自身の声を磨く技法だけではなく、聞き手との対話に焦点を当てて解説したいと思います。
指揮者から学ぶ、聞き手との対話
指揮者は、声を出さずして演奏者とコミュニケーションを取ることができます。「準備はいい?」「もっと大きく!」「抑えて」「楽しくなってきたね」「できる?」そんな風に、様々な想いや指示を身振りと目線で伝え、大勢を束ね、導くのです。
リーダー的立場や、情報を発信する側は、どうしても一方通行になりがちです。どんなスピーチやプレゼンであっても、ただ前を向いて熱弁したり、原稿を読んだりして正確に伝えるというだけでは、いくら感情を乗せたところで聞き手の都合にお構いなしの独りよがりなステージになってしまうと思いませんか?
聞き手が大勢いる場合、その1人1人は「私に話しかけているわけではなく、自分以外のみんなに向かって話しているんだなぁ」と思っています。
話の内容さえ伝えればいいのではなく、そういった人たちに、まず「私はあなたに向かって話しているんだよ!」と、伝えなくてはならないのです。
指揮者のように全体を把握しよう!

まず、これから自分の話を聞いてくれる人たちの顔を良く見て、全体を把握しましょう。誰がどこにいて、どんな顔をしているのか。
「みなさんこんにちは!!」と挨拶をしてみて、挨拶を返してくれる人がどれくらいいるのか。
そして、話の合間にどんな反応をしてくれるのか。
目は口ほどにものを言う、という言葉があるように、人間は、かすかな表情の変化を読み取ることができます。
「ふーん……そうなんだ」「納得行かないなあ」「どういうことだろう?」
そんな風に、口に出さなくても、表情を見れば何を考えているか分かりますよね。
一方的に話を進めるのではなく、聞き手が不思議そうな顔をしていれば解説を補足する、楽しそうであれば一緒に笑う、など、反応に反応をする、つまりはキャッチボールのように、投げたり、受け取ったりすることが大切なんです。
そのためには、自分の伝えたいことだけに集中するのではなく、指揮者のように余裕を持って周りを見渡し、全体を把握することが大切です。
キーパーソンを見つけよう!

大勢の聞き手は、皆それぞれの「聞き方」をしています。こちらを注視しているようで実はぼーっとしている人、こちらの話すリズムに合わせてうんうんと頷いている人、「へえ~」という表情をして、小さなリアクションを取ってくれている人、冗談を言えば笑う人。
まずは話しながら、何らかの反応を示してくれているキーパーソンを見つけましょう!
彼らに向かって話しかければ、一方的なスピーチではなく、上述した通り、キャッチボールのような対話になります。
「対話をしている」と自分自身で実感することによって、そのスピーチはより質の良いコミュニケーションに昇華するんです。
指揮者が目線と身振り手振りだけで的確な指示ができるように、スピーチにおいて聞き手と目線を合わせるということは、「私はあなたにボールを投げた。あなたからのボールも受け取るよ!」と示すことなんです。
聞いてくれない人の注目を集めよう!
キーパーソンのように初めから好意的に反応を示してくれない人も、もちろんいますよね。
寝ている人、起きてはいるけれど明らかに聞いていない人、そんな場合は、習得したテクニックを駆使して注目してもらいましょう。
人は変化に反応してしまうものですから、派手に抑揚を付けたり、緩急を付けたり、長い「間」を置いたりすれば、「んっ?」と瞬間的に意識を集中させます。
その瞬間を狙って目線を合わせ、話し続けることで、聞き手は「自分に向かって話しているんだ」と理解してくれますし、自然と聞く姿勢になってくれます。
相手が見えない場合はどうしたらいいの?

動画や音声配信は、リアルタイムとは限りませんし、聞き手の存在はこちらからまったく見えませんよね。
大勢の人に対して情報を発信しなければならないとき、どうやってコミュニケーションを取ればいいのでしょうか。
この場合、聞き手を想定して対話すること、問いかけることがポイントになってきます。
綺麗な文章にまとまっている原稿よりも、「話しかけられている」と思うようなスピーチの方が聞き手の心を掴むことができます。
「どう思います?」「ご存知ですか?」と要所で疑問を投げかけたり、「あっ、今、そんなはずないだろうって思いました?」と相手の立場からの想定をしたりするのもいいですね。